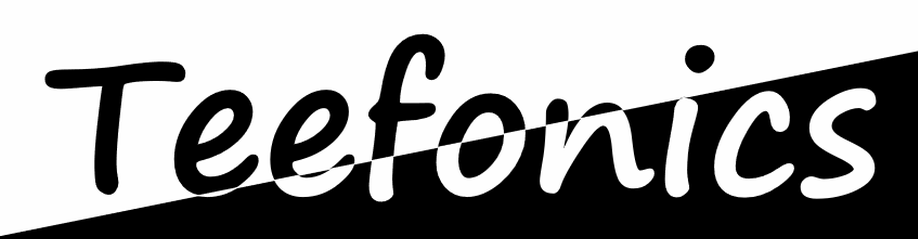09. バイトセンサの設定例
ここではバイトセンサの設定例をご紹介します。
共通事項
MWiCの使い方: 03. マウスピースの取り付けのところまではバイトセンサのモードにかかわらず共通です。リードに触れない状態と、しっかり押さえた状態のセンサデータの差が300以上あることが望ましい状況です。その条件さえ満たされていれば、Swingモードでは問題なく動作します。なお本ページ最後のセクションからリンクしております、開発アドバイザー@m_kirinoさんによる設定解説では、自在な演奏のためにバルーンをより出して、この値をかなり大きくする例を紹介しています。
MWiCの他の部分の操作に慣れるまで、まずはSwingモードで運用することをお勧めします。Swingモードにおける演奏感について、MWiCの設定から追加設定を行ってみてください。
Swingモードで基本的な演奏ができるようになったら、Track BendモードやReed Bendモードも試してみてください。
Track BendモードおよびReed Bendモードを初めて使う準備
Track BendモードやReed Bendモードを使う場合、LEDインジケータの設定を変更して、演奏しながらベンド状態が把握できるようにすることを強くお勧めします。少なくとも最初は以下の順番で設定して挙動を把握してください。
1.MWiCの設定: 18 Misc-1のG&B LEDsの設定を"P.Bend"にしてください。MIDIデータのピッチベンド値によってLEDの色が変化するようになります。MIDI音源にピッチベンドを表示する機能があれば合わせてご覧いただくと、さらにわかりやすいでしょう。Macをご利用、かつMainStageをお持ちの方は、@m_kirinoさんが『ウインドシンセ音源紹介 2 Mainstage』内で配布なさっているウインドシンセ用の設定ファイルをご利用頂くと大変わかりやすく、最初から良い音がなります。
- 緑: ピッチベンドニュートラル
- 消灯: 弱ピッチベンド
- 青: 明確なピッチベンド(ダウンでもアップでも)
2. Track Bendモードの待機状態はバイトセンサデータに関わらずニュートラルベンドです。そのため緑LEDが点灯します。
3. Reed Bendモードの待機状態はバイトセンサ値ゼロになります、そのためフルダウンベンドとなり、青色LEDが点灯します。
4. ただし赤色LEDでハーモニー状態を表示する設定(Red LED: Hamony)の場合、Track BendモードでもReed BendモードでもハーモニーがONの場合には待機状態のLED点灯色が赤色になります。
5. まずは挙動を把握するためにMWiCの設定: 08 Bite-1のFunctionをReed Bendに設定してください。Track BendモードはReed Bendモードに発音時ニュートラル補正が追加されたものに相当しますので、あとで試すことにしましょう。
6. MWiCの設定: 10: Bite-3を見ます。
7. 下ボタンを何回か押して右上のCurveにカーソルを合わせて、左右ボタンでカーブを選びます。Track BendモードやReed Bendモードでは平坦部があるカーブ10より上を使うのが現実的な選択です。テストとして12を選んでみます。
8. リードに触れていない状態でオクターブローラーに触れてバイトセンサのゼロ点を確定し、リードを指で押さえたり離したりします。デフォルトの設定であれば計測ラインが横軸の全範囲に移動するのが確認できます。ある範囲でデータが平坦部に乗ります。この状態がニュートラル状態の噛み具合となります。Bボタンを長押しして設定画面を終了(変更を確定)します。
9. 演奏してみて、リードの噛み具合と音程の関係をご確認ください。
10. ほとんどのMIDI音源では、リードを全く噛まない状態で音を出すとフルダウンベンドとなり半音2個分音程が下がります。グラフの平坦部まで噛むとニュートラルとなります。さらに噛むとアップベンドなりますが、デフォルトでは最大でも半音1個分しか音程が上がりません。これはMWiCの設定: 08 Bite-1の中のU/D Ratio設定が50%になっているためです。
11. テストのためBボタンを長押しして設定画面に移動し、このU/D Ratioの設定値を0(DownOnly)にしてみます。その場合アップベンドが全く生じないベンドダウンのみとなります。グラフの平坦部だけでなく、それより右側のカーブに沿ってどれだけ上がってもピッチはニュートラルのままです。
12. この状態で一度演奏してみてください。中間領域より強くかむ分には正しい音程が出ます。一方でアンブシュアを緩めるとベンドダウンは有効ですので、音程のキープとリードによるダウンベンドを両立しやすくなります。
13. アップベンドも使いたい、ということであればU/D Ratioをお好みの数値まで上げてお使いください。
14. 最後にTrack Bendモードを試します。Track Bendモードではローラーに触れることでゼロ点補正を行う機能はありません。いつでもバイトセンサは動作しています。その代わりに発音の瞬間の音程が正しくなるような補正を行います。息を吹き込む際にアンブシュアを締めるクセがあって、かつU/D Ratioがゼロでない場合、Track Bendモードでは音の出始めでピッチが上がりますのでご注意ください。
Track Bend モードで注意すること
Track Bendモードでほとんどリードを噛まずに発音してしまうと、リードの緩めしろがなくてフルベンドダウンできなくなります。ベンドダウンしたい場合には適切に噛んでから発音してください。また上述のように、発音の瞬間にアンブシュアが締まると音程が上がりますが、それは挙動としては正常です。
Reed Bendモードで注意すること
Reed BendモードではMWiCの設定: 08 Bite-1のCalib. Trigに設定した動作(デフォルトではローラーから指を離す)を行うとバイトセンサのデータが常にゼロになります。リードを噛む前にローラーに触れて、それからリードを噛む、という形で操作してください。中途半端に噛んでからローラーに触れるとそこがゼロ点(フルベンドダウン)であるかのように補正されてしまい、演奏上の支障となります。
開発アドバイザーによる解説
開発アドバイザーの@m_kirinoさんがno+eページ"Windsynth workbook"内で公開下さっている『MWiCメモ03 バイトセンサー調整-1』および『MWiCメモ04 バイトセンサー調整-2(リップベンド編)』は、本ページの内容を踏まえて、より包括的に、高度な演奏に向けての設定が解説されています。MWiCバイトセンサ設定のバイブルと言って過言ではありません。ぜひご参照ください。